092-260-5463
受付時間 10:00~18:00(平日)

 悩める若手社長
悩める若手社長就業規則と雇用契約書、内容が違ったらどちらを優先すればいいの?
法律との関係では、最終的に何が有効になるの?
こうした疑問を抱える企業担当者は少なくありません。どちらも大切な書類ですが、判断を誤ると従業員とのトラブルや法令違反につながりかねないため、正しい理解が欠かせません。
そこで重要になるのが、就業規則と雇用契約書の位置づけや優先順位を整理しておくことです。


社会保険労務士 志賀佑一
社会保険労務士志賀佑一事務所代表。
経営者、従業員、会社がともに3WINの組織づくりをモットーに、人材が定着する会社づくりのサポートに尽力。
社会保険労務士として独立後は人事労務支援に加え、各種研修や制度導入などを通じてリテンション(人材流出防止)マネジメント支援にも注力している。
最後まで読み進めれば、就業規則と雇用契約書をどう整理・整合させればよいかが分かり、法令に適合したうえで従業員に安心感を与える労務管理につなげられるはずです。
「うちの就業規則、昔に作ったままかも…」
「何を見直せばいいのか分からない…」
そんな経営者・人事担当者の方のために、
就業規則の見直しポイントを“ひと目で確認できる”チェックシートを作成しました。
✅ 制度が古く、現行法に合っていないリスク項目
✅ 働き方・休暇制度など、見直しが必要になりやすい章構成
✅ 社員トラブルを防ぐためのルール整備チェック
を、チェック式で簡単に確認できるようになっています。
今なら【無料】で「5分でわかる!就業規則セルフチェックシート」 をプレゼント中です!


自社の就業規則が「今の働き方」「法改正」に合っているか、まずはこのチェックシートで簡単にセルフ診断してみましょう。
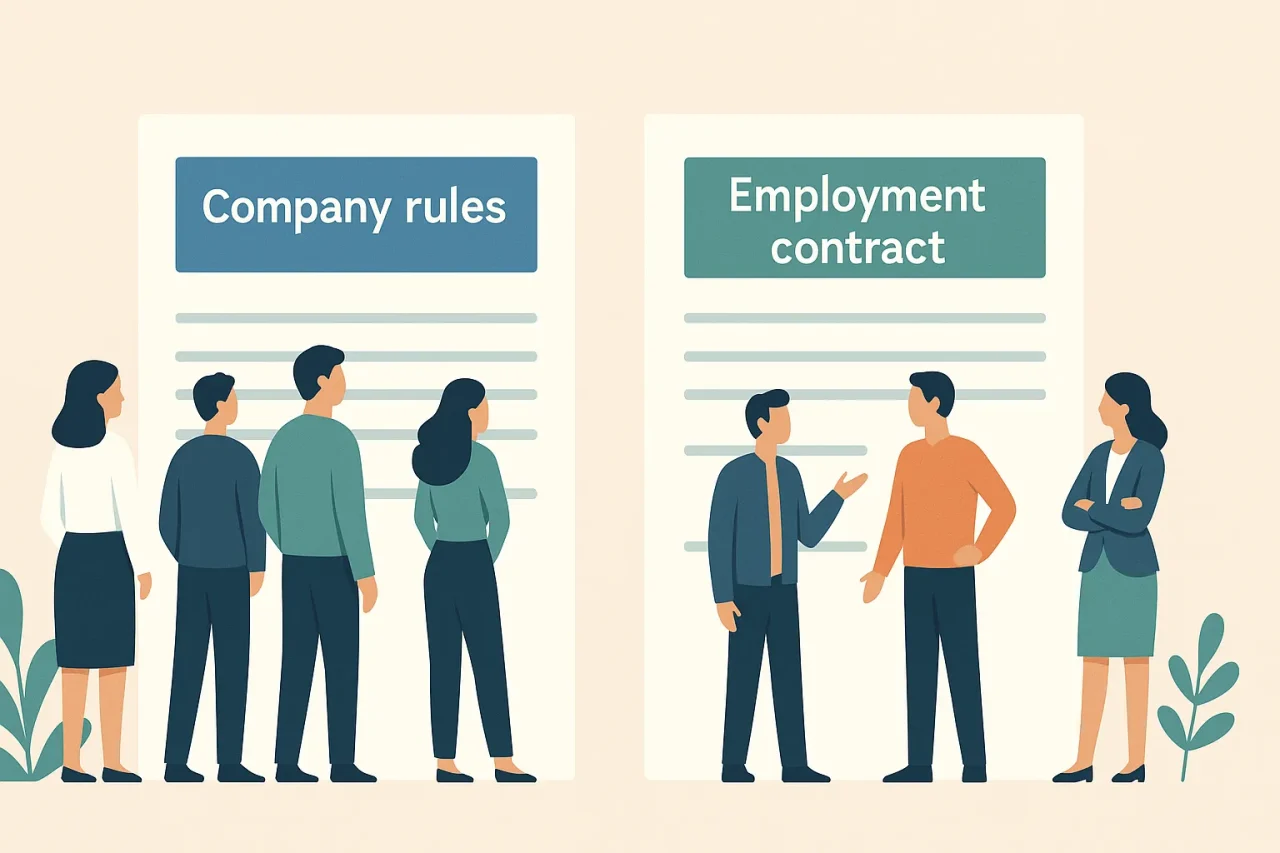
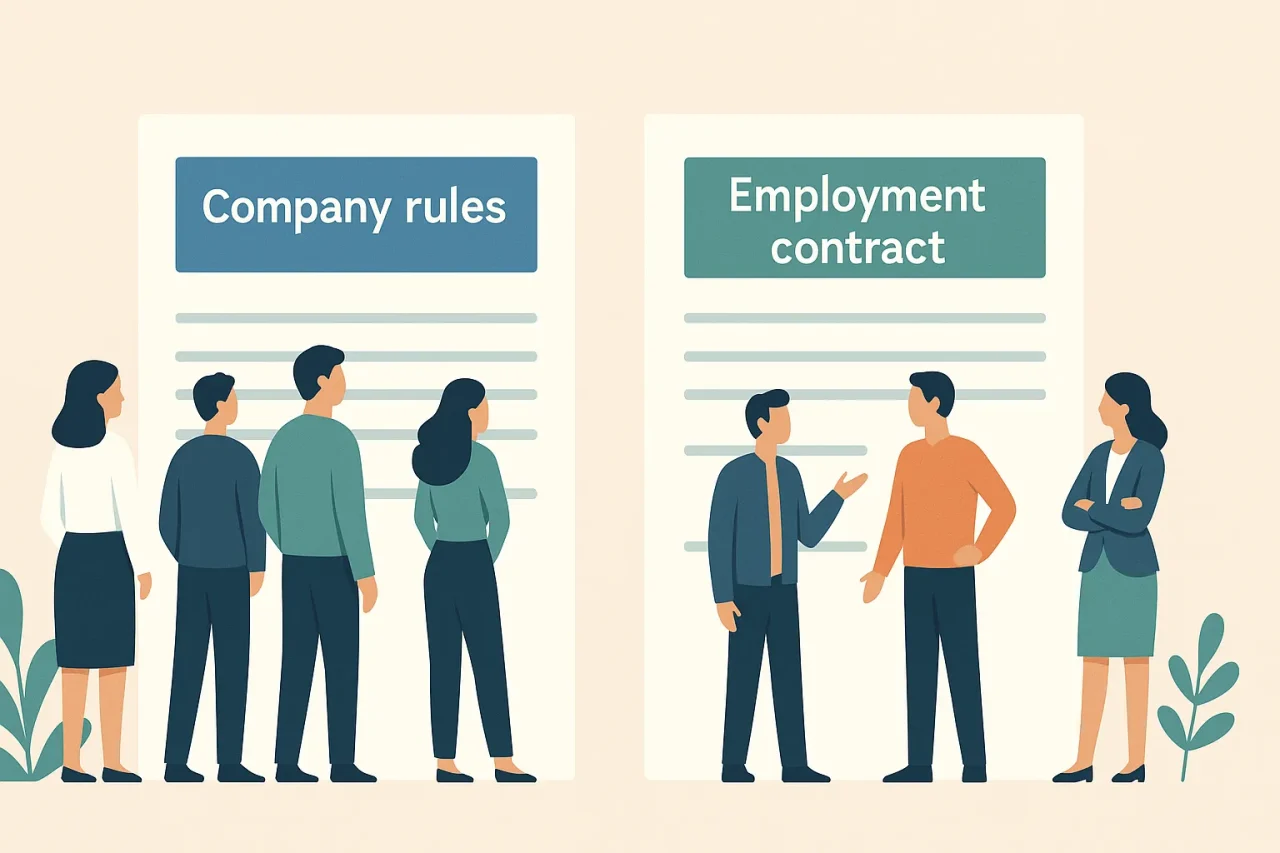
労働条件を確認するとき、まず押さえるべきは就業規則と雇用契約書の役割の違いです。両者は性質も対象範囲も異なるため、それぞれの位置づけを正しく理解することが重要になります。
企業で働くうえで必ず関わるのが「就業規則」と「雇用契約書」です。どちらも労働条件に深く関わる重要な文書ですが、役割と対象範囲が異なるため混同しないことが大切です。
就業規則
まず、就業規則は会社が従業員全体に適用する「共通ルール」をまとめたものです。勤務時間、休暇、賃金体系、安全衛生など、労働条件の基本的な取り扱いを網羅しており、会社全体のルールブックにあたります。一定規模以上の企業では、法律上作成・届出義務が課されています。
雇用契約書
一方で、雇用契約書は個々の従業員と会社が結ぶ「個別契約」です。就業場所、業務内容、給与額など、従業員ごとに異なる具体的な条件が記載されます。就業規則が「会社全体のルール」であるのに対し、雇用契約書は「個別の約束事」といえます。
イメージを整理すると次のようになります。
| 項目 | 就業規則 | 雇用契約書 |
|---|---|---|
| 対象 | 全従業員 | 個々の従業員 |
| 性質 | 会社のルールブック | 労働条件の個別契約 |
| 内容 | 勤務時間・休暇・賃金体系など一般的事項 | 就業場所・業務内容・給与額など具体的事項 |
| 法的義務 | 一定規模以上の会社に作成・届出義務あり | 法的義務はないが作成が望ましい |
このように、両者は「全体ルール」と「個別契約」という性質の違いを持っています。
企業が労務管理を適正に行うためには、この違いを理解し、双方の整合性を保つことが欠かせません。


就業規則と雇用契約書に矛盾が生じた場合、どちらを根拠とすべきか判断する必要があります。優先される基準を理解しておくことで、労使双方にとって公平な取り扱いが可能になります。
就業規則と雇用契約書の記載内容が食い違うことは珍しくありません。例えば、雇用契約書に書かれている条件と、会社全体に適用される就業規則の条件が一致しない場合です。
このような場合、
原則として従業員にとって有利な内容が優先されることが法律で定められています。
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
労働契約法|e-Gov 法令検索
ただし注意が必要なのは、雇用契約書が従業員にとって有利であっても、就業規則や法律に違反していれば無効になる点です。



つまり、「従業員に有利」かつ「法律に適合」していることが有効条件となります。
就業規則の内容が雇用契約書よりも従業員にとって好条件である場合は、就業規則が優先されます。典型的な例を挙げると以下の通りです。
就業規則が有利なケース
この場合、従業員にとって有利な「有給休暇20日付与」の規定が優先されます。
つまり、就業規則には「全従業員を守るための最低限かつ基本的なルール」が定められているため、雇用契約書に不利な条件や記載漏れがあったとしても、就業規則の基準を下回る内容は効力を持ちません。
企業としては、契約書を作成する際に就業規則との整合性を意識しないと、後にトラブルにつながる可能性がある点に注意が必要です。
雇用契約書の内容が従業員にとって就業規則よりも好条件である場合は、雇用契約書が優先されます。これは、個別の契約内容が従業員に利益をもたらす場合に、より有利な取り扱いを尊重するという考え方に基づいています。
たとえば以下のようなケースです。
雇用契約書が有利なケース
この場合、従業員にとって有利な「昇給・手当あり」の雇用契約書の内容が優先されます。
つまり、就業規則が会社全体のルールとして最低限の枠組みを示す一方で、雇用契約書は個々の事情に応じて条件を上乗せできる仕組みです。
企業としては、就業規則を基準にしつつ、個別の契約で柔軟に条件を設けることが可能だといえます。
就業規則や雇用契約書に記載されている内容が、労働基準法などの法律に違反している場合、その部分は無効となります。これは、法律が労働条件の最低基準を定めており、それを下回る約束は認められないためです。
たとえば、労働基準法では年次有給休暇の付与日数が最低基準として定められています。
仮に就業規則で「有給休暇なし」と定めていたり、雇用契約書に「有給を与えない」と記載していたとしても、その規定はすべて無効となり、法律の基準が適用されます。
つまり、どんなに合意があっても、法律に違反する労働条件は成立しないのです。



企業が就業規則や雇用契約書を見直す際には、まず「法律に適合しているか」を第一に確認する必要があります。
この観点を押さえることで、従業員とのトラブルを未然に防ぎ、健全な労務管理につなげることができます。


労働条件をめぐる書類は複数あり、それぞれ効力に上下関係があります。全体像を把握しておくことで、内容が食い違った際に迷わず正しい基準に立ち返ることができます。
労働条件を定める書類は複数存在しますが、それぞれの効力には明確な優先順位があります。この順序を理解しておくことで、内容が食い違った際にどちらを根拠とすべきか判断しやすくなります。
基本的な優先順位は以下の通りです。
| 優先順位 | 書類の種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1 | 法律(労働基準法・労働契約法など) | 労働条件の最低基準を定める。最も優先され、違反内容はすべて無効。 |
| 2 | 労働協約 | 労働組合と会社の間で結ばれる契約。法律に次ぐ効力を持つ。 |
| 3 | 就業規則 | 会社全体に適用されるルール。従業員に周知が必要。 |
| 4 | 雇用契約書 | 個別従業員との契約。就業規則より有利な内容であれば優先される。 |
このように、最上位は常に法律であり、その下に労働協約、就業規則、雇用契約書が続きます。
ただし、就業規則と雇用契約書については、従業員にとって有利な条件が優先されるという特別な関係性があります。
企業が労働条件を整理する際は、この優先順位を前提にしたうえで、書類同士の整合性を保つことが求められます。



特に法改正が行われた場合は、早急に規程や契約内容を確認し、必要に応じて改訂することが重要です。


就業規則や雇用契約書は作成したら終わりではなく、法改正や組織の変化に応じて適切に見直す必要があります。運用上のリスクを減らすためには、いくつかの観点から定期的な確認が欠かせません。
就業規則と雇用契約書は、どちらも従業員との労働関係を支える重要な基盤です。ところが、内容に不一致があると、従業員に不利と判断される場合は無効になるリスクがあり、企業側にとって不利な結果を招く可能性があります。
そのため、見直しの際には以下の観点が特に重要となります。
このような視点で確認を行うことで、トラブルを未然に防ぎ、企業として適正な労務管理を実現できます。
次にそれぞれ詳しく見ていきます。
就業規則と雇用契約書は、それぞれが独立した文書であると同時に、一体的に運用されるものです。どちらか一方だけを改訂すると、内容に齟齬が生じ、後に従業員とのトラブルにつながる恐れがあります。
特に、賃金体系や労働時間、休暇制度などの基本的な労働条件は、就業規則と雇用契約書の双方に記載されることが多いため、一貫性のあるルール設計が欠かせません。
また、法改正に伴う変更が必要となった場合は、就業規則と雇用契約書を同時に見直すことが必須です。例えば、労働条件明示ルールが改正された際には、契約書だけを直すのではなく、就業規則側にも整合性を持たせる必要があります。
企業にとっては、両者の整合性を維持することが、リスク回避と信頼性向上につながる重要な対応といえます。
賃金に関するルールは、就業規則・雇用契約書双方に記載されることが多く、法律の基本原則を理解することが前提になります。
賃金ルールの基本は以下の記事で確認できます。
企業が複数の雇用形態を採用している場合、雇用形態ごとに適切な就業規則と雇用契約書を整備することが重要です。
正社員、契約社員、アルバイトやパートなどは勤務時間や給与体系、契約期間に大きな違いがあるため、ひとつの就業規則や契約書だけでは実態に合わないケースが出てきます。
たとえば、パートタイム従業員に正社員と同じ規定が適用されると、想定外の労働条件を認めることになり、会社に不必要な負担やトラブルを招く可能性があります。



雇用形態に応じた規定を明確にすることで、従業員も納得しやすく、公平で分かりやすい労務管理が可能になります。
就業規則や雇用契約書には、法律で必ず明示しなければならない事項があります。これを怠ると、契約そのものが無効とされる可能性もあり、企業にとって大きなリスクとなります。
特に2024年4月の労働条件明示ルール改正により、就業場所や業務変更の範囲などが必ず明記すべき事項に追加されました。したがって、最新の法改正を踏まえたうえで、漏れのない記載が求められます。
代表的な明示事項は以下のとおりです。
絶対的明示事項(必ず記載が必要なもの)
賃金、労働時間、休日、就業場所など
相対的明示事項(該当する場合に記載が必要なもの)
退職金制度、休職制度、業務変更範囲など
企業としては、これらを正しく整理し、不備のない書類を整備することが不可欠です。
2024年4月の労働条件明示ルール改正では、就業場所や業務変更範囲の明示が義務付けられました。具体的な記載方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
(参考):厚生労働省|2024年4月から労働条件明示のルールが改正されます
就業規則や雇用契約書を改定する際に最も注意すべきなのは、従業員にとって不利益となる変更は原則として認められないという点です。労働契約法の規定により、会社が一方的に条件を悪化させることはできません。
ただし、以下のような要件を満たす場合に限り、例外的に変更が認められることがあります。
- 労働条件変更の必要性が客観的に合理的であること
- 変更内容が社会通念上相当と認められること
- 労働者への説明や意見聴取を十分に行っていること
それでも不利益変更は従業員の生活に大きな影響を与えるため、慎重な対応が求められます。
企業としては、まず従業員の合意を得る努力を優先し、合意形成が難しい場合でも、法律の要件を満たすかを慎重に検討する必要があります。
就業規則と雇用契約書は、どちらも従業員の労働条件を定める重要な書類です。内容が異なる場合は従業員に有利な条件が優先され、最終的には法律が最上位に位置づけられるという点を押さえておくことが欠かせません。
この記事のポイントを整理すると次のとおりです。
適切に整備された就業規則と雇用契約書は、従業員の安心と会社の信頼性を支える基盤です。優先順位の原則を理解し、法令に即した労務管理を実現することが、トラブル回避と健全な組織運営につながります。
当事務所では、就業規則や雇用契約書の整備・見直し、労働条件の適正化、法改正への対応をご支援しています。
といった課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。
無料相談をご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。専門の社会保険労務士が丁寧に対応し、貴社の状況に合わせたアドバイスをご提供いたします。
就業規則や雇用契約書の優先順位を正しく理解するには、関連する労務管理の知識もあわせて押さえておくことが大切です。以下の記事もぜひ参考にしてください。