092-260-5463
受付時間 10:00~18:00(平日)

 悩める若手社長
悩める若手社長 うちは月給制だけど、実際には出勤日数で給与が変わっている…
アルバイトに歩合給を導入してみたけど、最低賃金を下回ってないか心配…
評価制度と賃金が噛み合っていない気がする…
こうした賃金形態にまつわる不安やモヤモヤを感じている経営者・人事担当の方は、実は少なくありません。
多くの方が「給与の決め方の違い」程度に考えがちな賃金形態ですが、実際は、労働契約書の内容や割増賃金の算出方法、制度運用の整合性など、労務管理全体に大きな影響を及ぼす要素です。
制度にズレや曖昧さがあると、社員とのトラブルや法令違反リスクにもつながりかねません。
そのため、賃金形態は「とりあえず決める」のではなく、自社の働き方や雇用形態、評価制度との整合性をもとに丁寧に選ぶことが求められます。
「自社に合った賃金制度とは?」という疑問に答える一歩として、ぜひご活用ください。


社会保険労務士 志賀佑一
社会保険労務士志賀佑一事務所代表。
経営者、従業員、会社がともに3WINの組織づくりをモットーに、人材が定着する会社づくりのサポートに尽力。
社会保険労務士として独立後は人事労務支援に加え、各種研修や制度導入などを通じてリテンション(人材流出防止)マネジメント支援にも注力している。
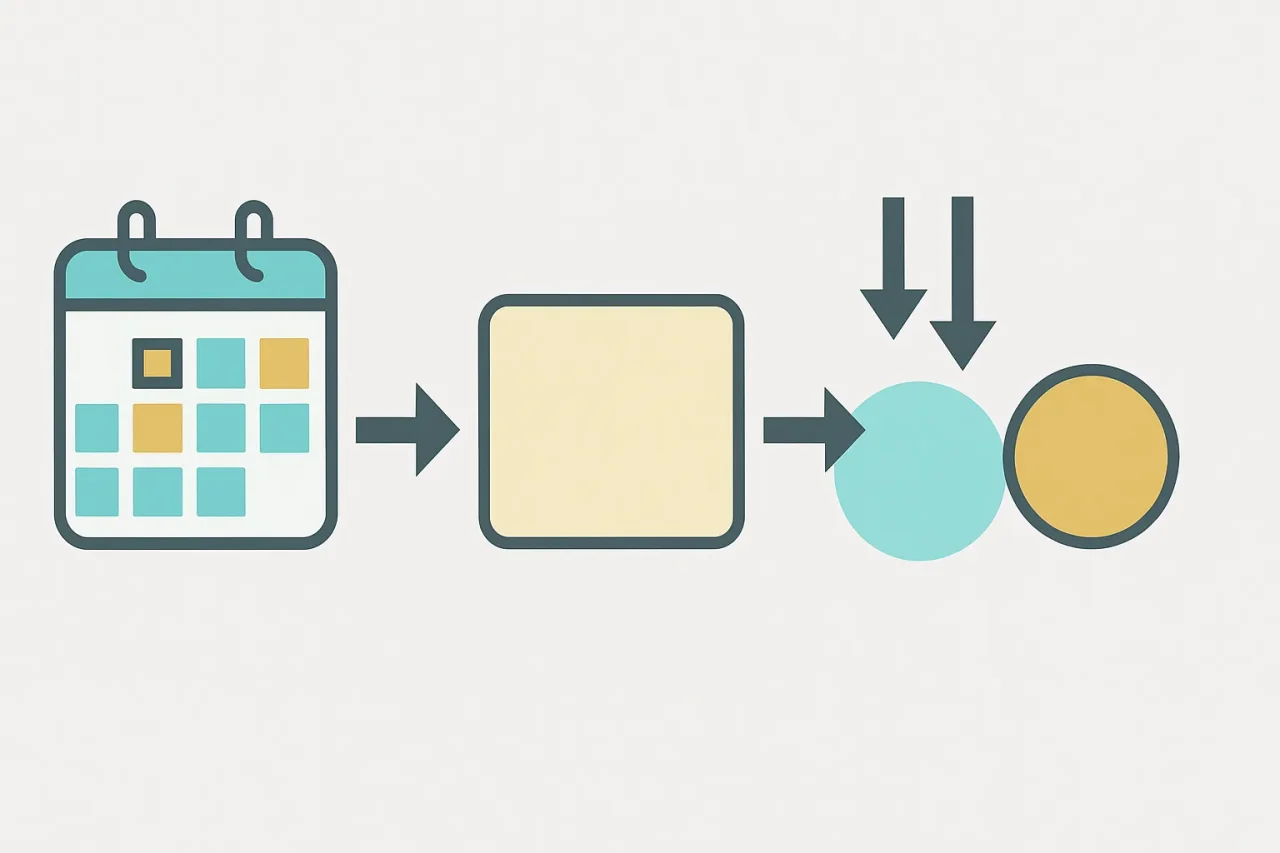
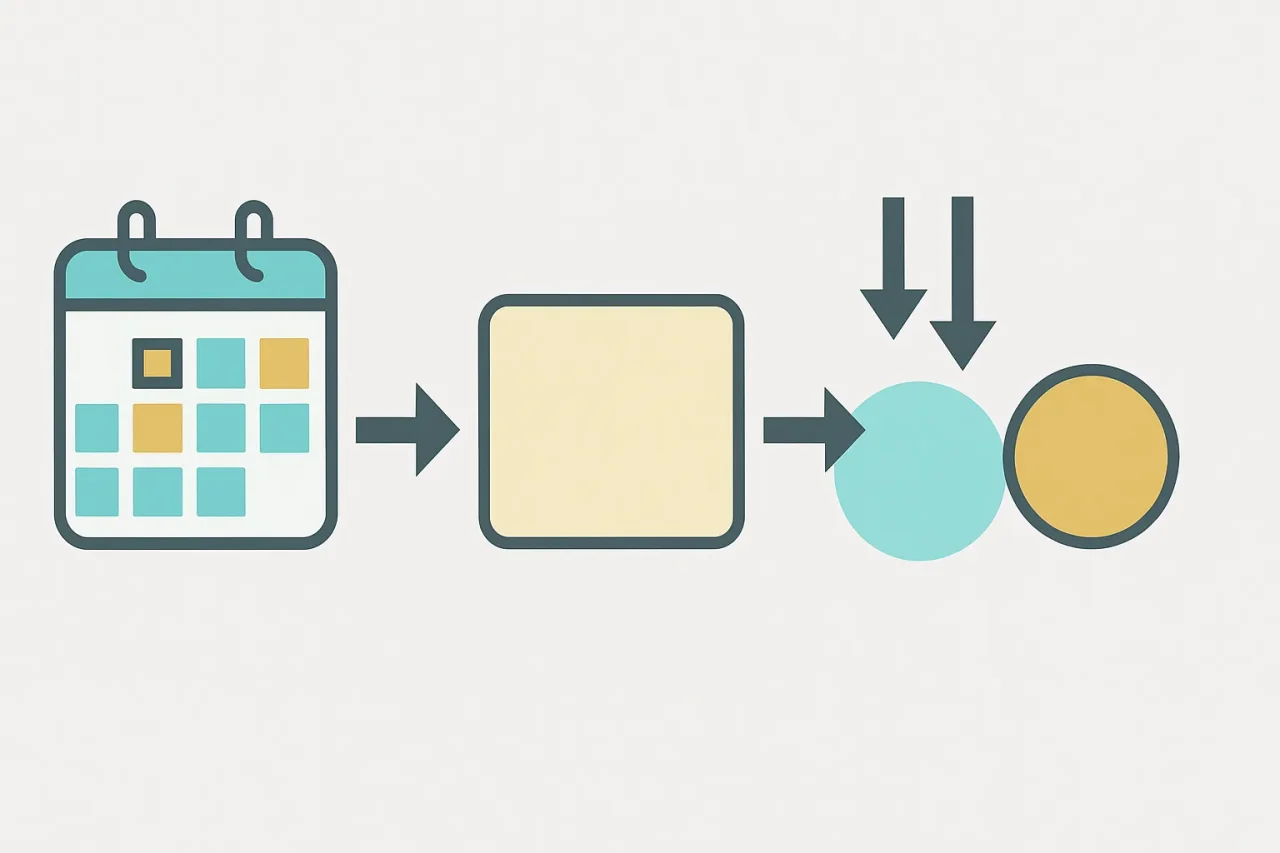
月給制とは、月単位であらかじめ決められた一定額の給与を支払う形態です。正社員や管理職など、継続的な雇用を前提とする職種で広く採用されています。
労働時間や日数にかかわらず、基本的には1ヶ月の労務提供に対して報酬を支払う設計であるため、安定性のある労働契約が構築しやすいという特徴があります。
月給制のメリットは以下の通りです。
月給制を採用していても、欠勤や遅刻、早退があった場合には、その分の給与を適切に控除する必要があります。そのためには、あらかじめ「日割計算」のルールを明確に定めておくことが不可欠です。
就業規則には、1日あたりの賃金の計算方法や控除の具体的な取り扱いについて、わかりやすく明文化しておく必要があります。こうしたルールが曖昧なままだと、従業員との間に誤解やトラブルが生じる恐れがあります。
また、制度上は月給制であっても、実際の運用が時給や日給のような管理になっている場合、外部からは実態として日給制または時給制と見なされる可能性もあります。制度と現場の運用にズレがないか、定期的に見直すことが重要です。
日給制は、働いた日数に応じて給与が決定する形態です。たとえば月に15日勤務した場合は、日給×15日分の給与が支払われるという仕組みです。
時給制は、1時間あたりの労働に対して報酬を支払う方式です。パート・アルバイト、派遣スタッフなどに広く利用されています。
両制度の使い分けは、雇用の安定性・勤務スタイル・業務の特性を基準に検討しましょう。


出来高制(歩合給制)は、従業員の仕事量や成果、業績に応じて賃金を決める制度です。完全出来高制のほか、「基本給+歩合」形式も一般的で、営業職や販売職など、成果を数値で評価できる職種によく採用されます。
メリットとデメリットは以下の通りです。
歩合制を採用する場合でも、最低賃金の保証は法律上の義務です。インセンティブ報酬だけを支給する形では、最低賃金法に抵触する可能性があり、注意が必要です。
また、歩合給であっても、残業・深夜・休日労働に対する割増賃金の対象に含めて計算する必要があります。そのため、単純に歩合率で成果報酬を算出するだけでは不十分であり、正確な時間管理と計算根拠の明示が求められます。
制度に一定の安定性を持たせるためには、「固定給+歩合給」のハイブリッド型を検討することが有効です。導入にあたっては、評価制度の整合性や営業目標の設定、業務量のコントロール可能性なども含め、総合的に制度設計を行うことが大切です。
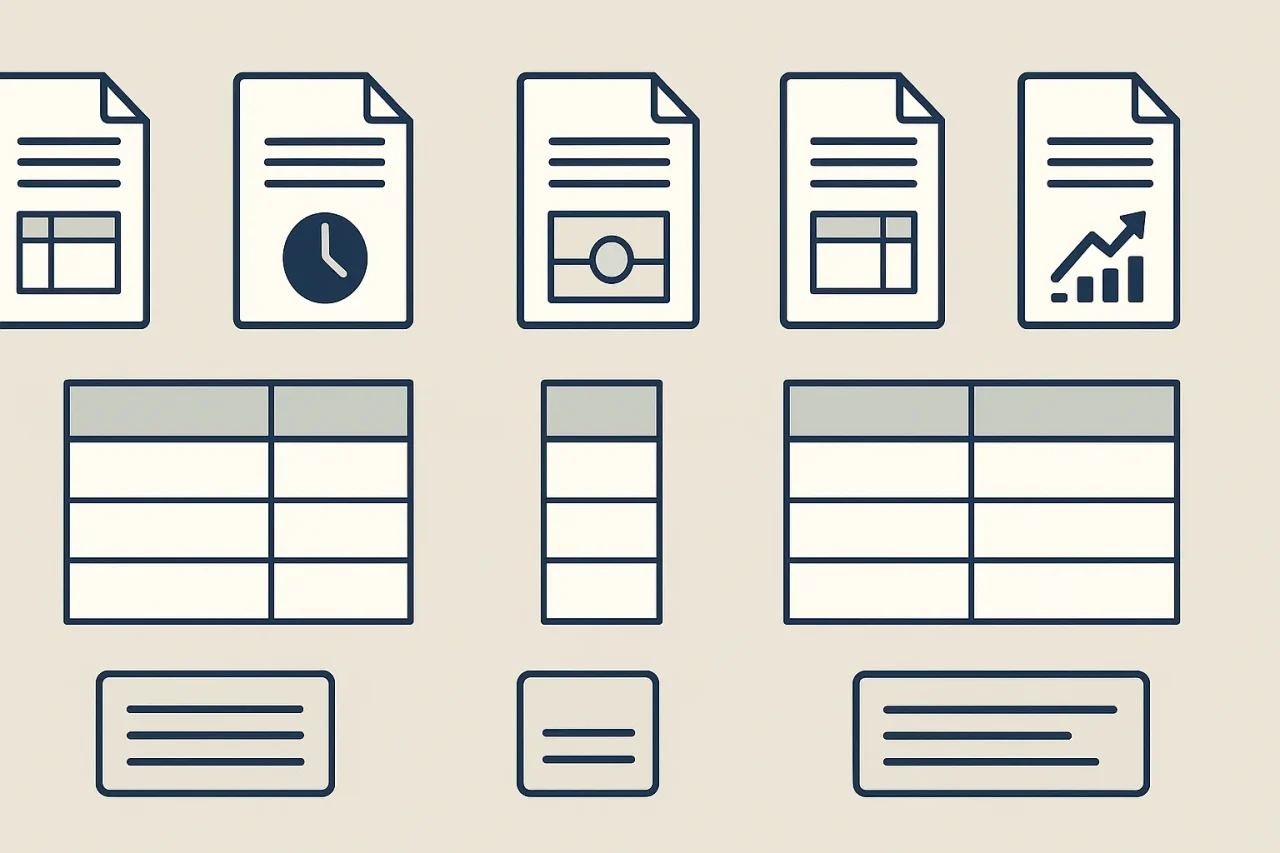
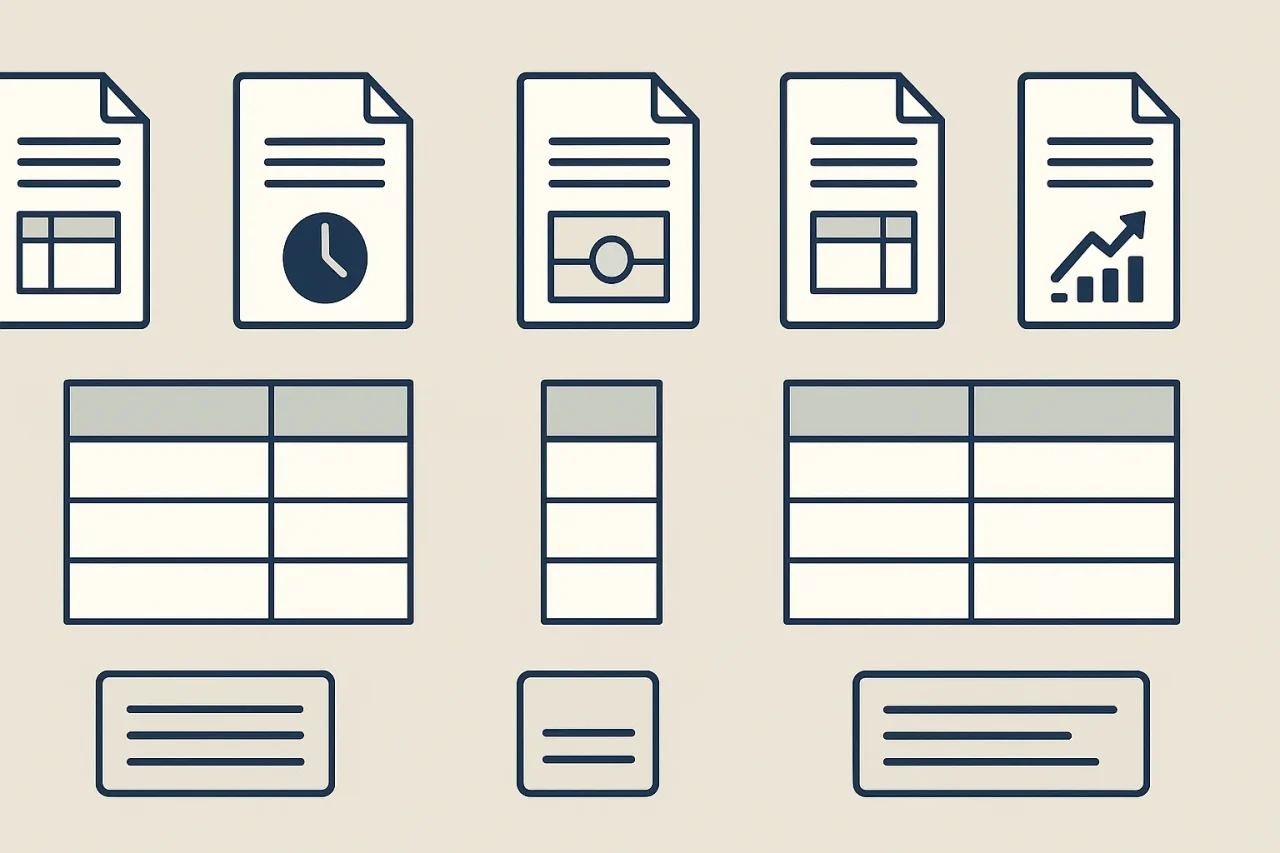
賃金形態によって、労働契約書や就業規則への記載内容も大きく変わります。制度を導入するだけでなく、文書としてきちんと整備されているかが、法令遵守とトラブル防止の要です。
なお、「賃金」とはそもそも何を指すのか、基本的な定義や構成について知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
賃金形態ごとの契約書への記載内容とポイントは以下の通りです。



契約書は「形式」ではなく、「実態と法令に合った内容」であることが大切です。必要に応じて専門家の確認を受けながら作成・見直しを行うことをおすすめします。
制度と実際の運用にズレがないかどうかは、定期的に確認することが重要です。必要があれば、就業規則や労働契約書の内容も見直し、適切に更新していく必要があります。
また、制度を変更する際には、従業員への丁寧な説明と同意の取得が不可欠です。制度の運用が曖昧なまま進められてしまうと、未払い賃金の発生や、労働基準監督署からの是正指導につながるリスクもあります。
こうしたリスクを回避するためにも、契約書や規程類の整備は「ただの形式」ではなく、制度の透明性と信頼性を支える土台としてしっかりと位置づけておくことが大切です。
賃金形態が違っても、割増賃金に関する法律の適用は一律です。
ただし、実際の計算方法は形態ごとに違いがあるため注意が必要です。
正確な割増賃金を算出するためには、労働時間の正確な記録と、支給額の内訳整理が重要です。
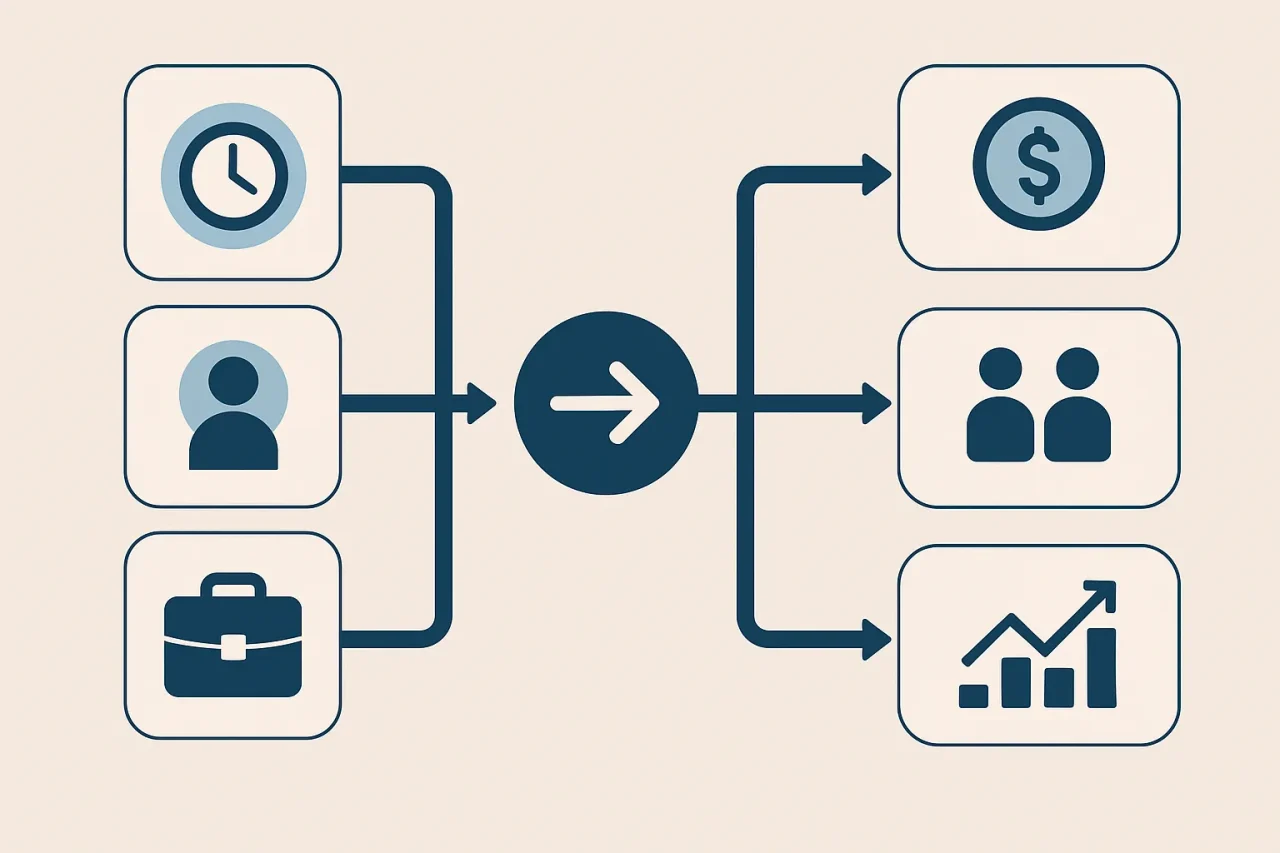
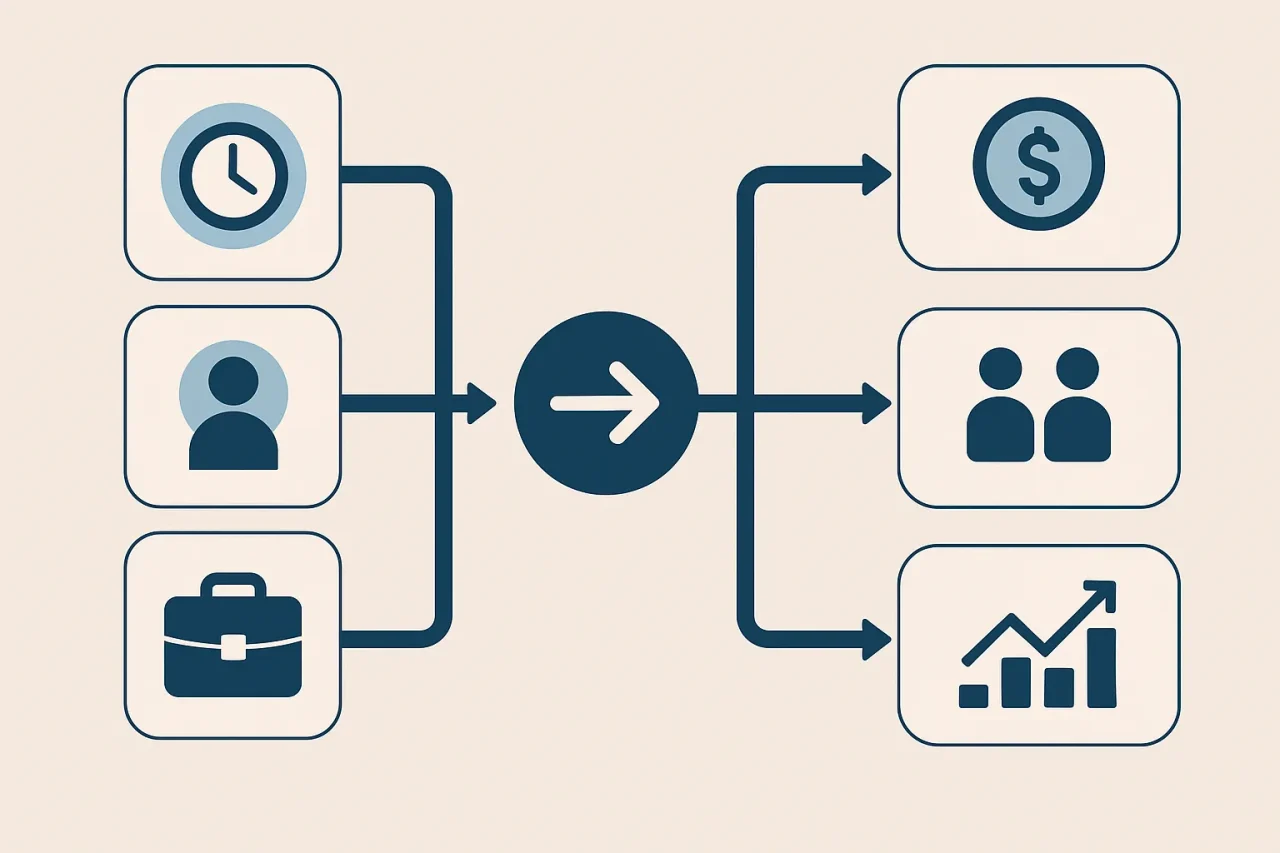
賃金形態を選ぶ際は、単に業種や慣習で決めるのではなく、自社の実態や運用目的に沿って検討することが重要です。以下の視点を参考にすると、より実効性の高い制度設計が可能になります。



制度を選ぶだけでなく、「誰が」「どう運用するか」まで見据えた設計が、長期的に機能する仕組みづくりの鍵となります。
賃金形態の選択は、企業の人事制度や働き方全体に大きく影響します。
制度を導入・変更する際は、単に給与の支払い方法を決めるだけでなく、契約内容や実際の運用と矛盾がないかを慎重に確認することが大切です。
ここでは、賃金形態を見直す前に押さえておきたいポイントを7つにまとめました。
どの賃金形態を採用するかは、自社の業務内容や従業員の雇用形態に応じて丁寧に検討する必要があります。
現在の制度が実態と合っているかを定期的に見直し、必要があれば契約書や就業規則の整備を進めましょう
賃金形態は単なる「給与の決め方」ではなく、労務管理全体の土台となる重要な制度設計の一部です。月給制・時給制・出来高制など、どの制度にも一長一短があるため、「これが正解」という万能の形は存在しません。
制度選びにおいて最も大切なのは、自社の働き方・業務内容・雇用形態・評価制度と整合性が取れているかという点です。
たとえば、営業職に歩合制を導入する場合でも、成果が安定しない時期の保証給の有無や、割増賃金の取り扱いをどう設計するかによって、法令遵守や社員満足度に大きな違いが出ます。
また、制度そのものだけでなく、
といった「制度と実態の一致」を常に意識することが、トラブル防止と企業信頼の維持につながります。
賃金制度は、一度決めたら終わりではありません。法改正、事業拡大、人員構成の変化などに応じて、定期的に見直し・再構築することが重要です。
「今の制度、見直したほうがいいかも?」と少しでも感じたら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
✔ 月給制だけど、実態は日給・時給っぽくなっている
✔ 歩合給を導入しているけれど、最低賃金や割増賃金の計算が不安
✔ 新しい評価制度と賃金制度がうまくかみ合っていない気がする
こんなお悩みがひとつでも当てはまる場合は、制度の見直しを検討するタイミングかもしれません。
私たちは、これまで多数の企業の制度設計や労務トラブルの未然防止をサポートしてきました。制度のプロである社会保険労務士が、現状分析と改善のヒントをご提供します。
▶︎ 【無料】制度のカンタン診断はこちら
\制度に潜むリスクを“見える化”してみませんか?/
ぜひお気軽にご相談ください。