092-260-5463
受付時間 10:00~18:00(平日)
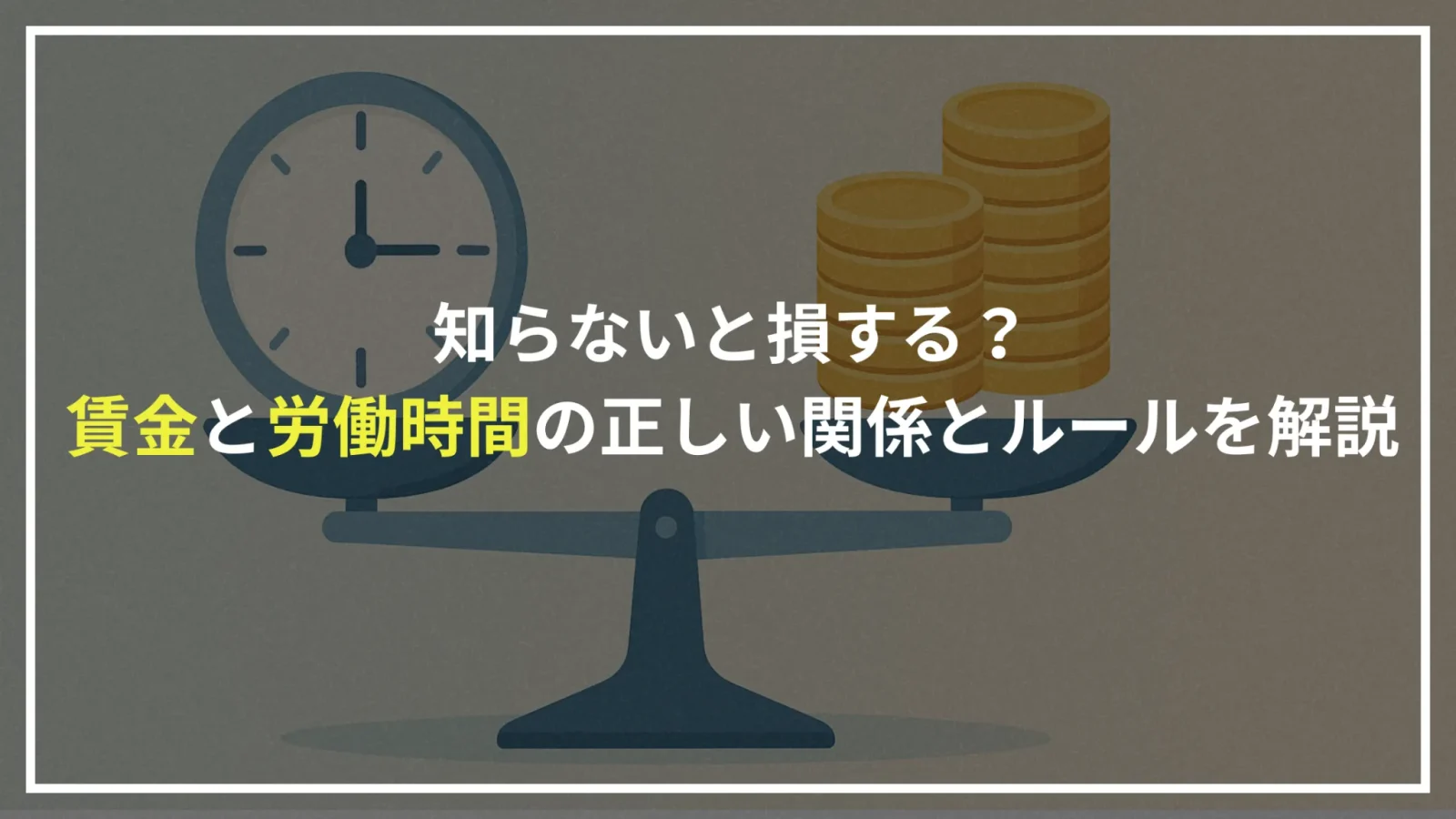
 悩める若手社長
悩める若手社長 残業代って、どこから発生するの?
所定労働時間と法定労働時間の違いがあいまい…
うちは“残業代込み”の月給だから大丈夫だと思ってたけど、本当に問題ないのか不安…
給与計算や労働時間の管理において、こうしたお悩みやご質問はとても多く寄せられます。
一見シンプルに見える「労働時間」と「賃金」の関係ですが、制度の理解があいまいなまま運用を続けてしまうと、未払い賃金や労使トラブルにつながるリスクがあります。
本記事では、そうした不安を解消すべく、「労働時間と賃金の正しい関係」をわかりやすく整理しました。
現場の実情をふまえた実務的な視点で、制度の基本からトラブル回避のポイントまで解説します。


社会保険労務士 志賀佑一
社会保険労務士志賀佑一事務所代表。
経営者、従業員、会社がともに3WINの組織づくりをモットーに、人材が定着する会社づくりのサポートに尽力。
社会保険労務士として独立後は人事労務支援に加え、各種研修や制度導入などを通じてリテンション(人材流出防止)マネジメント支援にも注力している。
給与計算において、最も基本となるのが「労働時間に応じて賃金を支払う」という考え方です。しかし実際には、“単に働いた時間”だけでなく、その時間の内容や属性によって支払う賃金の中身は変わってきます。
たとえば同じ1時間でも、
となります。
このように、「どの時間帯に」「どの条件で」労働が行われたかを区別することが、正確な給与計算の第一歩です。
管理体制があいまいだと、未払い賃金や計算ミスに気づかないまま運用が続き、後からトラブルが表面化することも。
まずは「賃金=時間×内容」であるという原則を、社内全体で共通認識にしておくことが重要です。
「うちは所定労働時間を超えて働いたら残業代を払っているから大丈夫」とお考えの方も多いですが、実はここに落とし穴があります。
多くの企業で混同されやすいのが、「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いです。
この2つは似ているようで、役割がまったく異なります。
たとえば、所定労働時間が7時間の企業で、社員が1日8時間働いた場合、
これが「法定内残業」と呼ばれるケースです。
逆に、法定労働時間を1分でも超えた場合は、割増賃金(25%以上)の支払い義務が発生します。



この違いを理解していないと、過剰な支払いや未払いによる法令違反のリスクが出てきます。制度の意味を社内で共有し、就業規則や雇用契約書にも正確に反映させましょう。


「残業代はどの時点で支払う必要があるのか?」という疑問は、企業担当者から非常によく寄せられます。
割増賃金が必要になるタイミングは、以下の2つです。
つまり、「所定の時間を超えたらすぐ残業代」というわけではなく、法定労働時間との関係で支払い義務が決まるのです。
特に注意したいのは、「休日」と一括りにせず、法定休日か所定休日かを正確に区別して運用すること。ここを曖昧にすると、残業代の計算ミスや未払いの原因になります。
割増賃金が発生するのは、以下の3つのパターンです。これらのいずれに該当しても、通常賃金に加えて割増分を支払う義務があります。
また、深夜×時間外や深夜×休日のように、複数の割増条件が重なった場合は、割増率の合算(例:25%+25%=50%)が求められます。
このような条件が複雑になる場面では、システム任せにせず、設定内容やルールの根拠を明文化しておくことが肝要です。
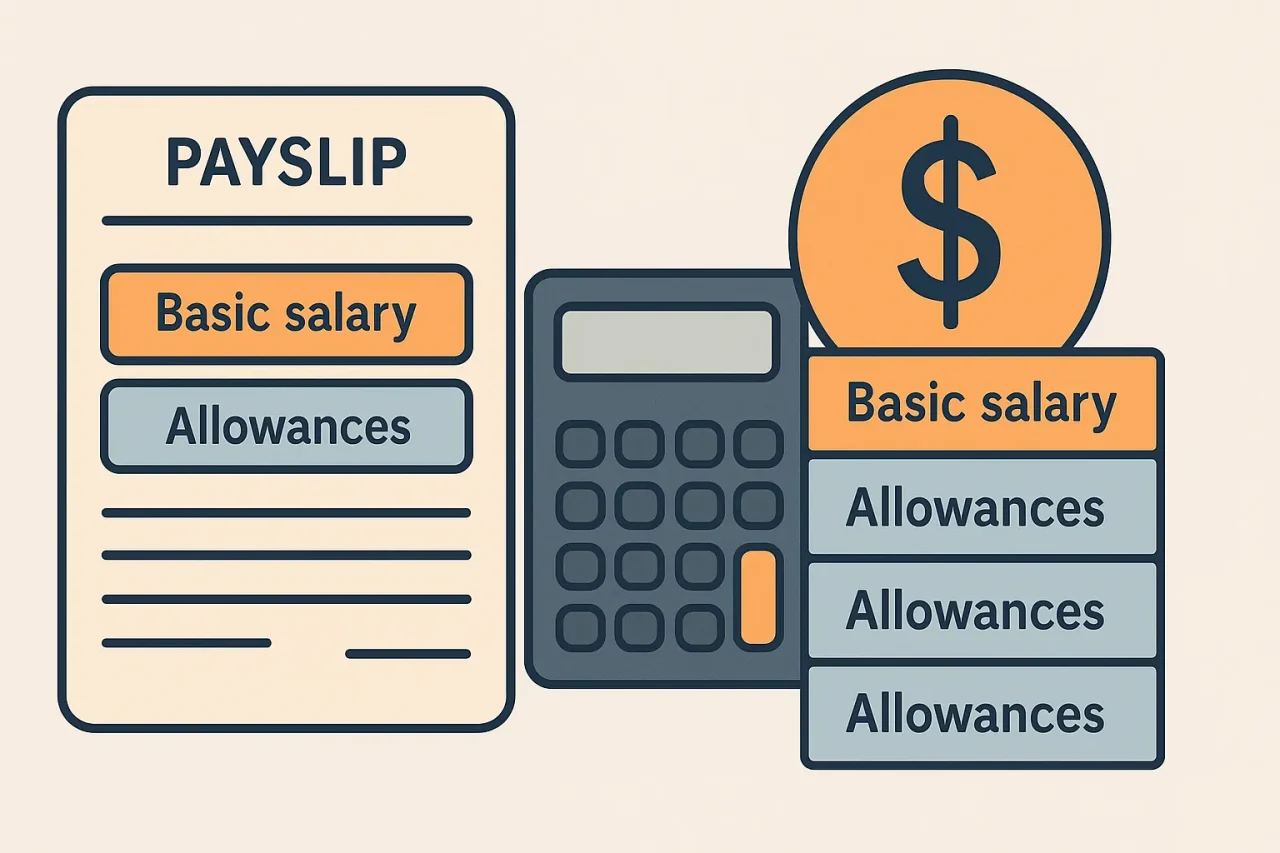
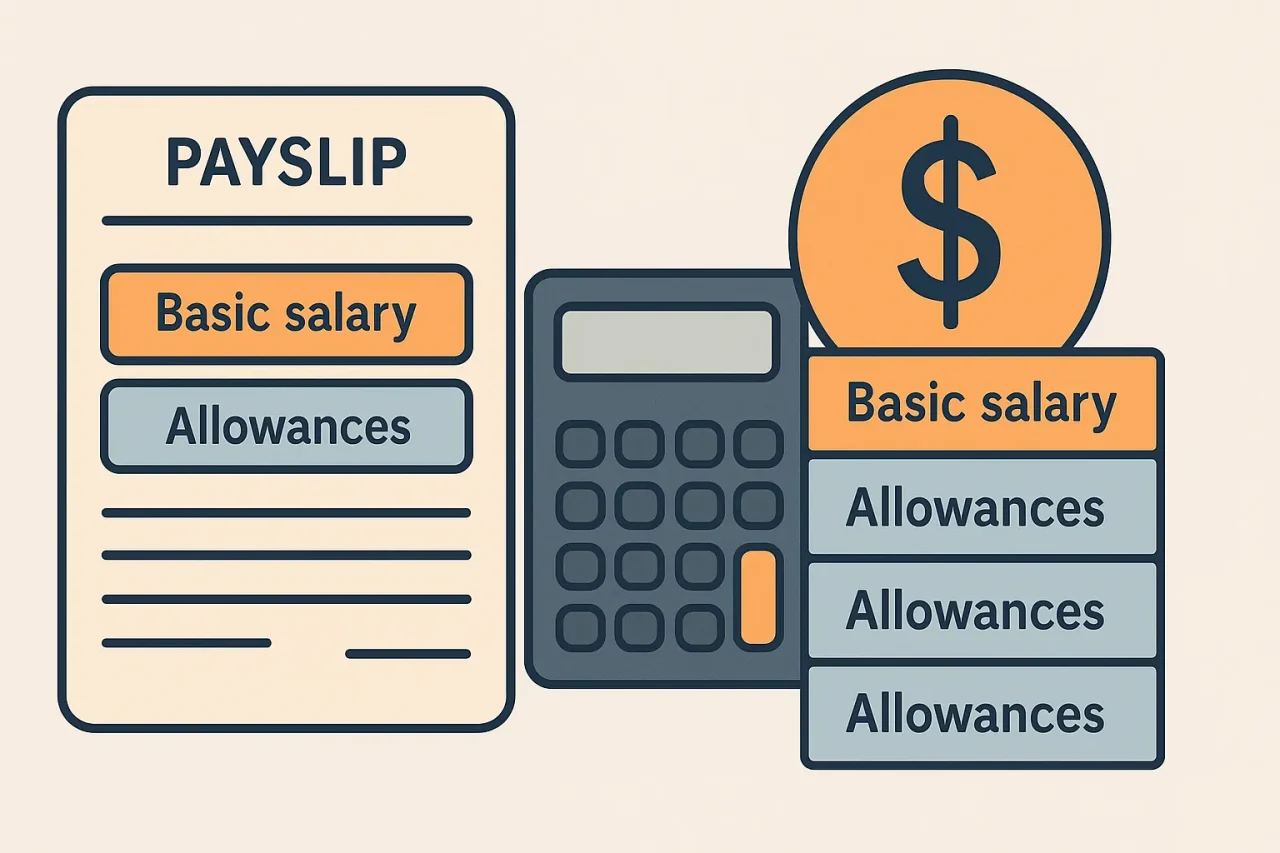
割増賃金を計算するうえでの起点となるのが、「時間単価(1時間あたりの賃金)」です。この時間単価が正しく算出されていなければ、割増計算そのものが不正確になり、法違反の原因になります。
基本式は以下のとおり。
ここで注意が必要なのは、「月給」の中に何を含めるかです。
この区別を誤ると、時間単価が低く見積もられてしまい、結果的に割増賃金の未払いが発生するリスクがあります。
就業規則や賃金規程に、「時間単価の構成要素」をあらかじめ定義しておくと、トラブル防止に役立ちます。
なお、そもそも「賃金」とはどこまでを指すのか、定義や構成要素についてあらためて確認したい方は、こちらの記事も参考になります。
割増率の正しい理解は、給与計算の根幹です。以下に代表的な割増率をまとめます。
| 労働内容 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(法定超え) | 25%以上 |
| 深夜労働(22時〜5時) | 25%以上 |
| 休日労働(法定休日) | 35%以上 |
| 月60時間超の時間外労働 | 50%以上(※中小企業は猶予) |
| 深夜+時間外、深夜+休日など | 割増率を合算して適用 |
割増率の「合算」が必要になるケースでは、システムによる自動計算の設定漏れが原因で、未払いが長期間にわたって蓄積することもあります。
こうした事態を避けるためにも、人事・労務部門で割増対象労働を定期的にチェックする体制が求められます。


変形労働時間制とは、1日の労働時間を柔軟に設定できる制度です。
たとえば「ある日は6時間勤務、別の日は10時間勤務」という働き方も、週全体・月全体で法定労働時間に収まっていれば割増不要となります。
主な制度タイプは以下の通り。
ただし、導入には厳密なルールがあり、適正な手続きが行われていない場合はすべての超過労働が割増対象になるおそれがあります。
変形労働時間制を導入していても、“制度が有効に成立していなければ”無効扱いとなり、多額の残業代請求につながる可能性もあるため、導入後の運用状況の定期確認も必須です。
みなし労働時間制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間数を「働いたものとみなす」制度です。営業職や出張の多い職種で使われます。
適用される主なパターンは以下の3つです。
特に注意が必要なのが、「事業場外みなし労働時間制」です。
この制度が成立するためには:
が要件となります。
たとえば、営業職であっても、上司との同行や日報で細かく行動管理されている場合は、“みなし”として成立しない可能性があります。
また、制度の導入時には、
などを事前に整理し、制度として文書化することが重要です。
「うちは残業代込みの月給だから問題ない」と安心していませんか?
このような“固定残業代制”は、労働基準法上も認められた制度ですが、要件を満たしていなければ制度自体が無効とされることがあります。
正しく制度を運用するには、以下3つのポイントを必ず押さえる必要があります。
実際には、これらのいずれかを満たしていないケースが非常に多く見られます。形式だけ整えた“名ばかり固定残業代”には要注意です。
固定残業代制度を導入・運用する際は、労働条件通知書での明示も重要なポイントです。記載方法に不安がある場合は、以下の記事をご覧ください。
制度は導入しているものの、運用が正しく行われていないことが、労使トラブルの大きな原因になります。
たとえばこんなケースがあります:
これらはすべて、不適切な設計・説明不足・運用のずれによって起こるものです。トラブルを未然に防ぐためには:
「説明していたつもりだった」「昔からそうしている」では通用しません。“仕組み”と“運用”の両輪で制度を回すことが重要です。
勤怠管理は、賃金計算・残業代支払いの“元データ”です。ここにミスがあると、いくら制度設計が完璧でも意味がなくなってしまいます。
よくあるミスとしては:
こうした状態が続くと、社員が退職後に「実際はもっと働いていた」と未払い請求する事例も少なくありません。記録の曖昧さ=会社の弱みになります。
さらに、「申請主義」や「承認制」があるから大丈夫と思っていても、労働実態が伴っていなければ認められないケースもあります。
労働基準監督署では、“実際に働いたかどうか”が最重視されます。
もう一つ見落とされがちなのが、「割増の判断基準は週単位である」という点です。
労働基準法では、1週40時間を超えた時間に対して割増賃金が必要とされています。月単位で残業時間を集計していても、週単位での管理ができていなければ、割増計算が不足するリスクがあります。
特に注意したいのが:
対策としては:
週40時間の壁を意識した勤怠管理体制に変えることで、計算ミスやトラブルの未然防止につながります。
「これは労働時間に入るのか?」という問いは、業種・職種によって頻出する悩みです。
基本的な考え方は次のとおりです:
グレーゾーンになりやすい具体例をいくつかご紹介します:
誤ってこれらを「労働時間外」としてしまうと、賃金の未払いリスクが高まります。



労働時間に関する定義は“実態ベース”で判断されるため、就業規則や社内マニュアルにしっかり反映させることが必要です。
こうした判断が分かれる場面では、「うちの会社ではどう取り扱うか」を明文化しておくことが最大の防止策になります。
明文化がされていないと:
そのため、
こうした備えが、いざという時に会社を守る明確なルールとなります。
賃金に関するトラブルを防ぐためには、基本となる「賃金支払いの原則」を押さえておくことも大切です。ルールの再確認はこちらの記事をご覧ください。
従業員に支払う給与がどのように決まるのか、また労働時間との関係をどう管理すべきか――企業の労務管理において、見落としがちな基本の一つです。
特に、「残業代の発生条件がよく分からない」「所定と法定の違いがあいまい」といった声は、現場から多く寄せられます。



本記事のまとめでは、そうした実務上の疑問や誤解が生じやすいポイントを整理し、給与と労働時間の仕組みを正しく運用するために必要な知識をわかりやすくご紹介します。
労働時間と賃金の取り扱いは、従業員との信頼関係を築くうえでも非常に重要な要素です。実務でのミスや認識のズレが、後々のトラブルや未払い問題に直結してしまうこともあります。
この機会にぜひ、自社の制度や運用方法を見直してみてください。
そんな企業様のために、就業規則・賃金規程の簡易診断や、労働時間制度の無料相談も随時受付中です。
といったお悩みに、社会保険労務士が実務視点で対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。