092-260-5463
受付時間 10:00~18:00(平日)

就業規則を作成したものの、
 悩める若手社長
悩める若手社長「どこに、どうやって届け出ればいいのか分からない」
「うちはパートも含めて10人以上だけど、届出の対象になるの?」
「電子申請は使えるの?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
就業規則の届出は、会社の労務管理における法令遵守の第一歩です。しかし、提出の対象や必要書類、手続きの流れを正確に理解していないと、知らぬ間に違反状態となってしまうこともあります。
この記事では、次のポイントを中心に、社労士の視点からわかりやすく解説します。


社会保険労務士 志賀佑一
社会保険労務士志賀佑一事務所代表。
経営者、従業員、会社がともに3WINの組織づくりをモットーに、人材が定着する会社づくりのサポートに尽力。
社会保険労務士として独立後は人事労務支援に加え、各種研修や制度導入などを通じてリテンション(人材流出防止)マネジメント支援にも注力している。
読み終わった後には、就業規則の届出に関する全体像が整理され、自社に合った方法で確実に届出を完了できる状態になるはずです。
「うちの就業規則、昔に作ったままかも…」
「何を見直せばいいのか分からない…」
そんな経営者・人事担当者の方のために、
就業規則の見直しポイントを“ひと目で確認できる”チェックシートを作成しました。
✅ 制度が古く、現行法に合っていないリスク項目
✅ 働き方・休暇制度など、見直しが必要になりやすい章構成
✅ 社員トラブルを防ぐためのルール整備チェック
を、チェック式で簡単に確認できるようになっています。
今なら【無料】で「5分でわかる!就業規則セルフチェックシート」 をプレゼント中です!


自社の就業規則が「今の働き方」「法改正」に合っているか、まずはこのチェックシートで簡単にセルフ診断してみましょう。


就業規則の届出は、一定規模以上の事業場に課される法的義務です。従業員数の基準や判断方法を正しく理解しておくことで、届出漏れによるリスクを防止できます。
就業規則の届出は、労働基準法で義務付けられた手続きです。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出ることが法律上の義務となります。
ここで重要なのは、「就業規則を作るだけでは足りない」という点です。労働条件を明文化した規則を作成したうえで、「監督署に届出を行い、さらに従業員へ周知する」ことで初めて法的効力を持ちます。
また、この「労働者」には正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなどの非正規社員も含まれます。雇用形態ではなく、実際に労働契約を結んで働いているかどうかが判断基準となります。
なお、届出の対象となる書類は以下の3点です。
| 書類名 | 内容・目的 |
|---|---|
| 就業規則本体(本則) | 労働時間・休日・賃金など基本ルールを定めた規程 |
| 意見書 | 労働者の意見を聴取したことを証明する書類 |
| 就業規則届(または変更届) | 労働基準監督署に正式に届け出るための書類 |
これらの書類を2部ずつ(正本・写し)準備し、提出後は受理印を押された控えを保管しておくことが必要です。
届出義務が発生する「10人以上」の数え方は、会社全体の人数ではなく事業場単位で判断します。
つまり、本社・支店・営業所など、それぞれの拠点ごとに10人以上の労働者がいるかで届出の要否が決まります。
たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。
| 事業場 | 従業員数 | 届出義務 |
|---|---|---|
| 本社 | 15人 | 必要 |
| 支店A | 12人 | 必要 |
| 支店B | 5人 | 不要 |
この場合、本店と支店Aだけが届出の対象となります。
また、本社と支店で同じ就業規則を使用している場合でも、各事業場で意見書を取得する必要があります。
注意すべきは、常時10人以上という文言の「常時」です。
一時的に増減する繁忙期や短期雇用ではなく、継続的に10人以上が在籍している状態を指します。
季節要員などを含めて基準を超えるかどうか迷う場合は、平均的な人員をもとに判断し、必要に応じて専門家や労働基準監督署に確認すると確実です。
この基準を誤ると、「届出漏れ」として指導の対象になることもあります。自社が該当するかどうかを事業場単位で慎重に確認しておくことが重要です。
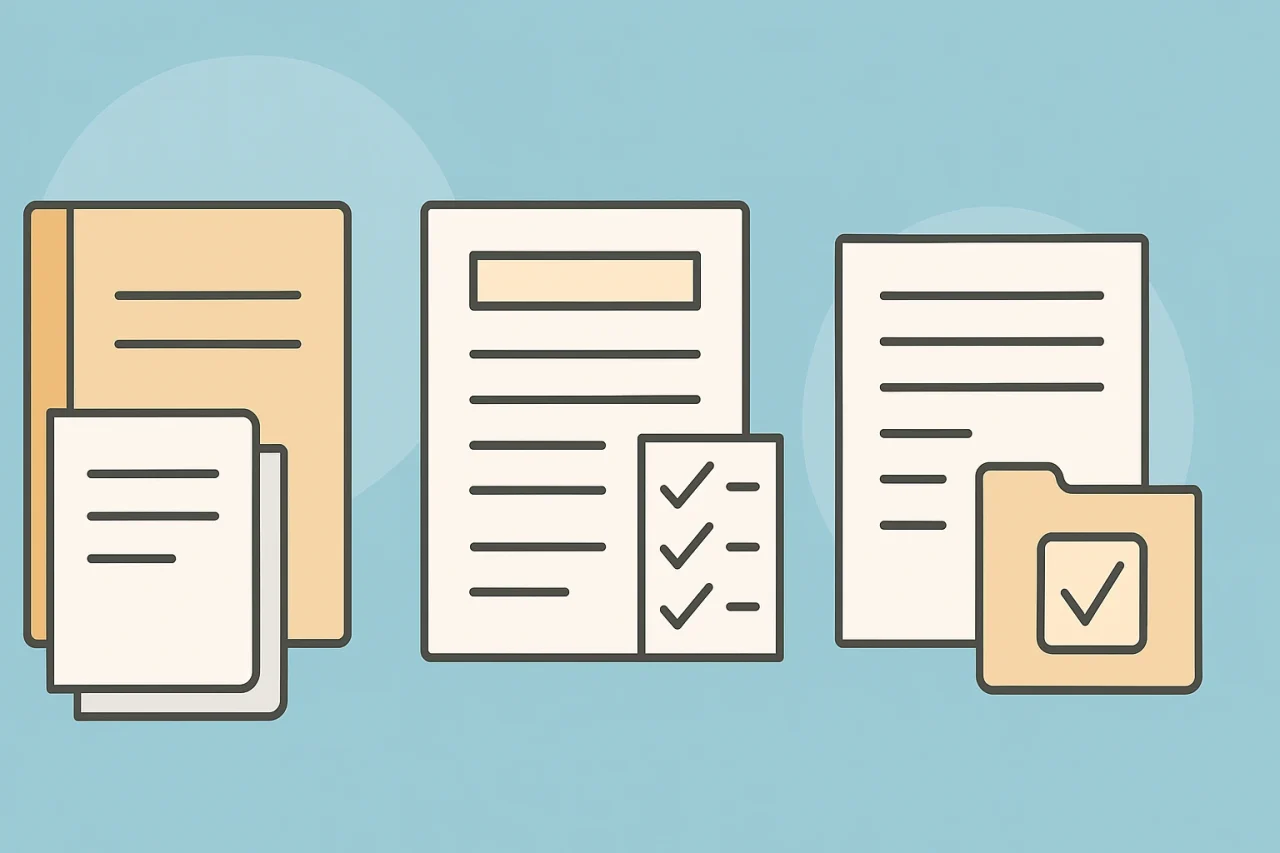
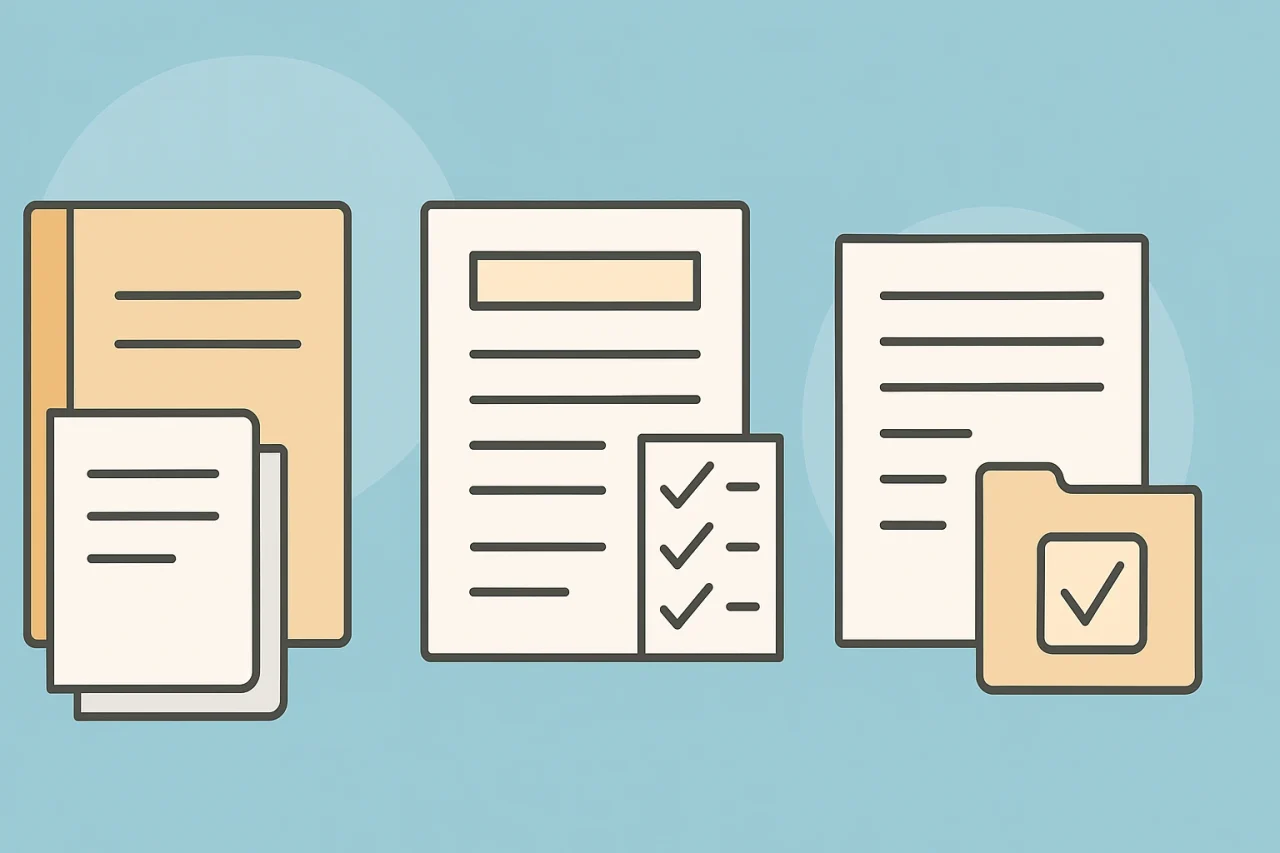
就業規則を労働基準監督署へ提出する際は、決まった書類一式を揃える必要があります。形式よりも「内容の整合性」と「証拠としての正確性」が求められる点がポイントです。
就業規則の本体は、いわば会社の「ルールブック」にあたるものです。労働時間、休日、賃金、退職など、従業員の労働条件を明確に示す基準として重要な役割を果たします。
労働基準法では、就業規則に定めなければならない事項を「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に区分しています。
| 区分 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 絶対的必要記載事項 | 労働時間・休憩・休日・賃金・退職など | すべての事業場で必ず記載が必要 |
| 相対的必要記載事項 | 退職金・表彰・懲戒・安全衛生など | 定める場合のみ記載が必要 |
特に注意したいのは、「相対的必要記載事項」をあえて記載しない場合でも、会社としてルールが存在するなら明文化すべきという点です。
たとえば、懲戒処分や表彰制度を運用している場合、文面に落とし込まれていなければトラブルの原因になります。
また、就業規則を作成する際は、最新の法改正(例:育児・介護休業法、労働時間の上限規制など)を反映することが欠かせません。



古いテンプレートを流用すると、知らないうちに法令違反となるリスクがあるため、定期的な見直しをおすすめします。
就業規則を届け出る際には、労働者の意見を聴取した証拠として「意見書」の添付が義務付けられています。この書類は単なる形式ではなく、労使間の信頼関係を示す重要な意味を持ちます。
意見書には、次の内容を記載します。
ここでポイントとなるのが、「労働者代表の選び方」です。法律上、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者が対象となります。
労働者代表を選出する際は、会社が任命するのではなく、従業員の中から民主的な手続き(投票・挙手など)で選ぶ必要があります。
会社側の意向で決めた代表は「適正な代表」と認められない可能性があるため注意が必要です。
また、意見書の内容は「反対意見があっても無効になるわけではない」点も誤解されがちです。意見を聴いたという事実自体が法的要件となるため、反対意見があっても提出することは可能です。
意見書の作成や労働者代表の選び方は、就業規則の届出において誤解されやすい部分です。代表者の選出方法や記載手順をより具体的に知りたい方は、以下の記事も参考になります。
就業規則を労働基準監督署に届け出る際は、「就業規則届(または変更届)」の提出が必要です。この書類は届出の表紙のような役割を果たし、就業規則や意見書とセットで提出します。
特定の書式は法律で定められていませんが、各地の労働基準監督署や厚生労働省のウェブサイトからテンプレートをダウンロード可能です。
会社独自の書式を使用しても問題はありませんが、記載内容に漏れがないよう注意が必要です。
主な記載項目
特に変更届を提出する場合、変更箇所と理由を明記すれば全文提出は不要です。ただし、複数箇所を改定した場合は、分かりやすいように該当箇所を赤字や下線で示すなどの工夫が望まれます。
なお、届出は正本・写しの2部を提出し、受理印が押された写しを自社で保管しておくことが原則です。これにより、監督署への届出が完了した正式な証拠として扱うことができます。
届出が必要なのは本則だけではありません。賃金や休業制度などを定めた付属規程も、労働条件に関わる場合は同様に提出対象となります。
就業規則を届け出る際は、その「本体(本則)」だけでなく、付属する規程も届出の対象となる点に注意が必要です。
これらの付属規程は、就業規則と一体として労働条件を定めているため、労働基準法上も同等の扱いを受けます。
代表的な届出対象の付属規程には、次のようなものがあります。
| 規程名 | 主な内容 | 届出の要否 |
|---|---|---|
| 賃金規程 | 基本給・手当・賞与・昇給などの賃金体系 | 必要 |
| 育児・介護休業規程 | 育児休業・介護休業の取得条件や手続き | 必要 |
| 退職金規程 | 退職金の支給基準・算定方法 | 必要 |
| 安全衛生規程 | 職場の安全管理や健康管理のルール | 必要(就業条件に関係する範囲) |
これらはいずれも労働条件や待遇に直接関わる内容を定めているため、就業規則と同様に届出を行わなければなりません。特に賃金規程や休業規程は法改正の影響を受けやすく、改訂時にも都度届出が必要です。
一方で、同じ「社内ルール」でも、業務手順書やマニュアルなどのように労働条件そのものを定めていない文書は届出の対象外となります。
すべての社内規定が届出の対象となるわけではありません。
労働条件に直接関係しない社内ルールや運用マニュアルは、原則として届出の必要はありません。
たとえば、以下のような規定や文書は「届出不要」と判断されます。
これらは従業員の労働条件そのものを規定しているわけではなく、業務の運用や社内文化を整えるためのルールに過ぎません。
ただし、判断が難しいケースもあります。たとえば「在宅勤務規程」や「副業規程」などは、労働時間や賃金に関係する内容が含まれている場合は届出が必要です。



もし届出の要否で迷う場合は、労働基準監督署または社会保険労務士に確認することをおすすめします。
誤った判断のまま届出を怠ると、後から是正を求められることもあるため注意が必要です。
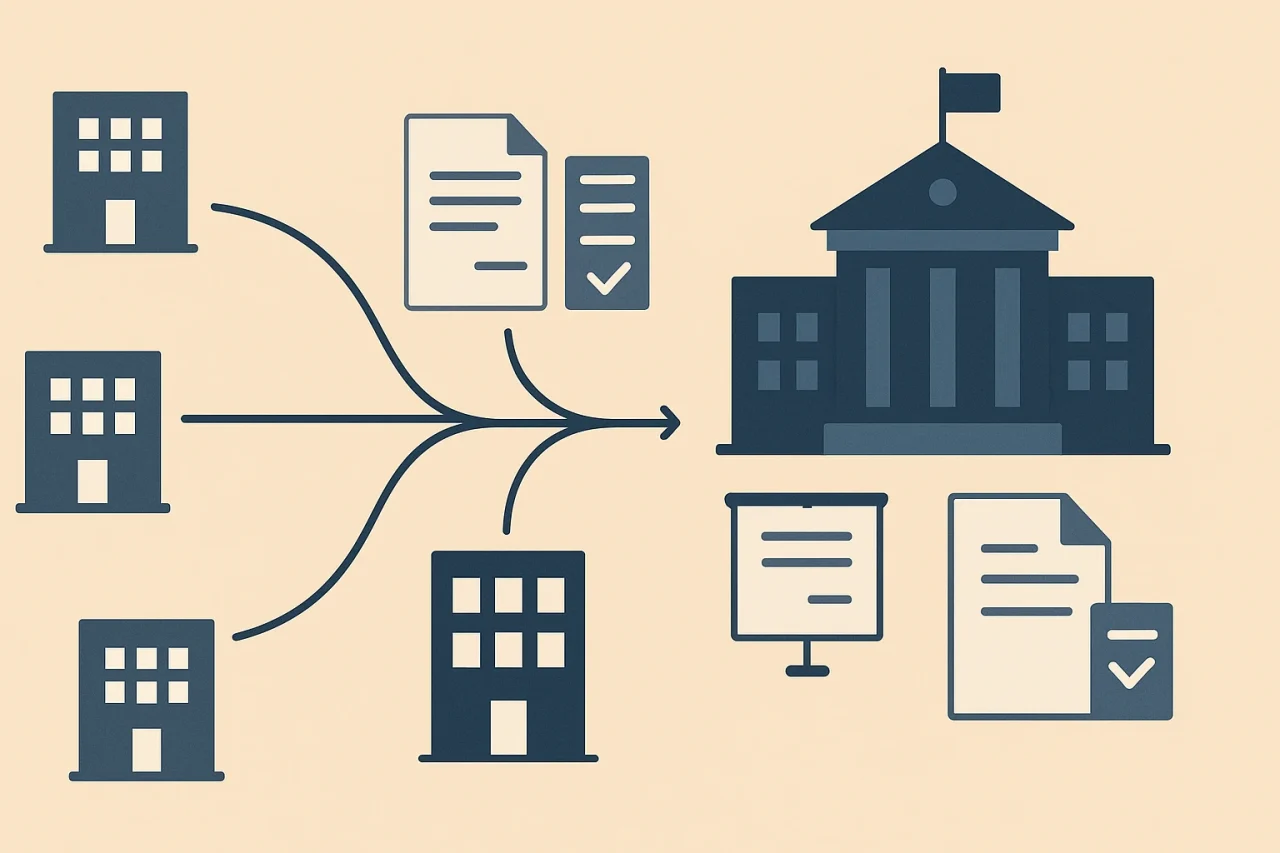
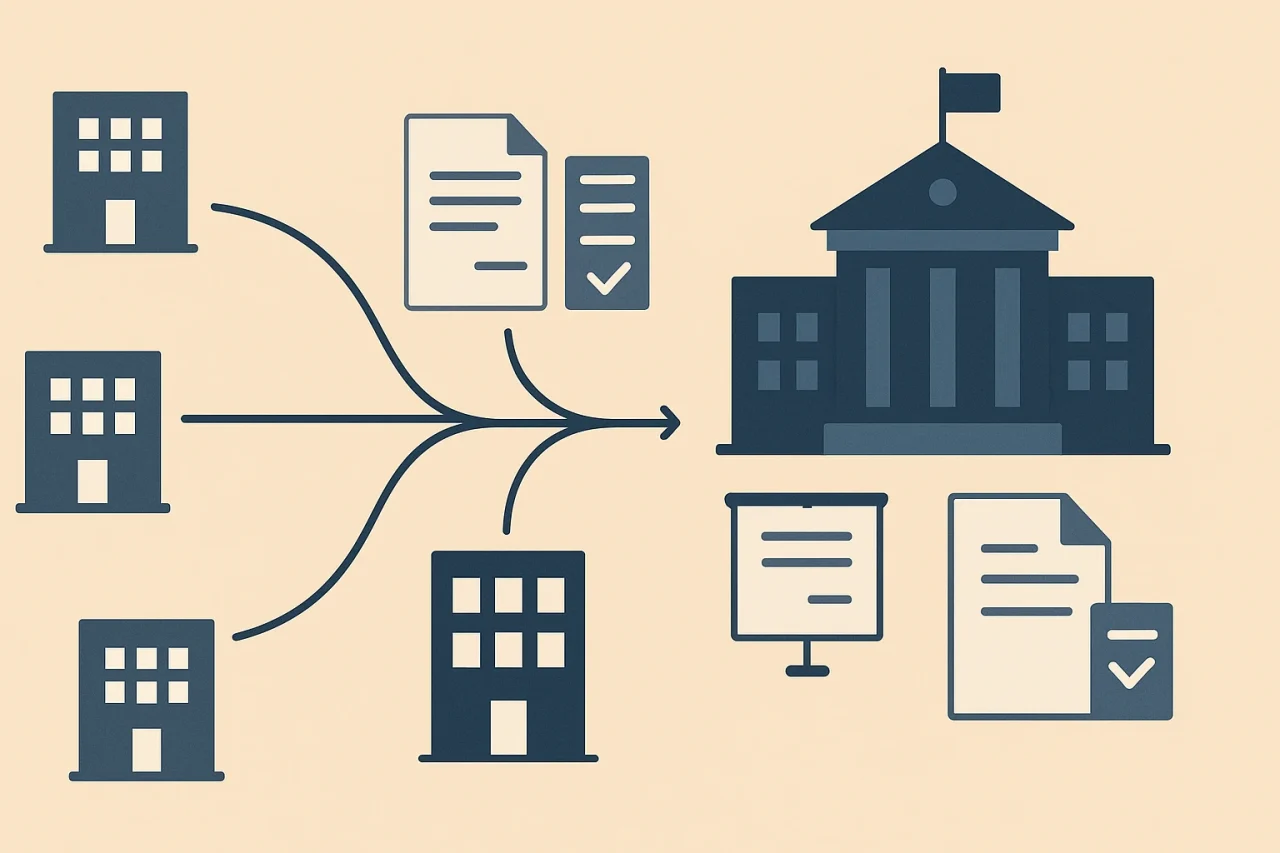
複数の事業場を持つ企業では、本社でまとめて就業規則を届け出ることが可能です。一括届出の仕組みを正しく活用すれば、業務負担を減らしながら法令遵守を徹底できます。
複数の事業場を運営している会社では、各拠点で同一の就業規則を使用している場合に限り、「本社一括届出制度」を活用できます。
これは、各事業場ごとに個別提出する手間を省き、本社がまとめて就業規則を労働基準監督署へ届け出る仕組みです。
利用できるのは、以下の要件を満たしている場合に限られます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 就業規則の内容がすべての事業場で同一であること | 部署・支店によって内容に差がある場合は対象外 |
| 各事業場において労働者代表から意見書を取得していること | 代表の署名がある意見書が必要 |
| 本社が全体を統括し、各事業場の労務管理を行っていること | 労働契約・人事制度などが本社主導で統一されていること |
この制度を使えば、各支店がそれぞれ届出を行う必要がなく、本社でまとめて提出できるため、実務負担を大幅に軽減できます。
一方で、事業場ごとに異なるルールを運用している場合には利用できません。たとえば、支店Aのみフレックスタイム制度を導入している場合などは、一括届出の対象外です。
本社一括届出は便利な制度ですが、「全事業場で就業規則が同一であること」が前提となるため、適用可否を慎重に判断することが重要です。
本社一括届出を行う際には、提出書類の扱いに注意が必要です。各事業場で意見書を取得していても、本社でまとめる段階で不足や記載漏れがあると受理されないことがあります。
提出時には、以下の書類をセットで揃えるのが原則です。
特に意見書は、すべての事業場分を添付する必要があります。一括届出といっても、代表意見書1枚だけで代替することはできません。
また、届出先は本社を管轄する労働基準監督署となります。一部の会社では、「支店所在地の監督署にも控えを送付しておく」といった運用をしているケースもありますが、これは義務ではなく任意です。



注意すべきポイントとして、届出後の変更や改訂時にも同様の手続きが必要になることが挙げられます。
一括届出を利用している企業は、就業規則を改定した際にも、各事業場から再度意見書を取得し、本社でまとめて提出する流れとなります。
制度の利便性を活かすためにも、各事業場での意見書取得や書類管理の体制をあらかじめ整えておくことが実務上のポイントです。


就業規則の提出方法には、窓口・郵送・電子申請の3パターンがあります。それぞれに特徴とメリットがあり、自社の運用環境に合わせて最適な方法を選択することが重要です。
最も確実で安心な方法が、労働基準監督署の窓口に直接持参して提出する方法です。
特に初めて就業規則を届け出る場合は、窓口提出をおすすめします。担当者がその場で内容や添付書類の不備を確認してくれるため、修正が必要な場合でも即座に対応できるからです。
提出先は、事業場を管轄する労働基準監督署です。複数の支店がある場合、それぞれの所在地を管轄する監督署に提出する必要があります。
提出時の注意点
窓口での提出は担当官とのやり取りができるため、初回提出や変更内容が複雑な場合にも安心です。
就業規則の届出は、郵送による提出も認められています。ただし、書類のやり取りに日数がかかるため、余裕を持ったスケジュールで行うことが大切です。
郵送提出の手順
返信用封筒には、会社名と返送先住所を明記し、十分な切手を貼っておきます。監督署で受理印が押された控えが返送されれば、届出完了の証明となります。
また、書類に不備がある場合は差し戻しになることもあるため、提出前に記載内容や添付漏れを必ず確認しましょう。
最近では、電子政府の総合窓口(e-Gov)を利用した電子申請も広く活用されています。この方法は、24時間いつでも申請でき、紙の提出や郵送が不要という大きなメリットがあります。
電子申請の流れ
申請後、監督署側で受理が完了すると、受理印が押された控えをデータでダウンロードできます。
電子申請には、事前にgBizIDなどの電子証明書の取得が必要ですが、近年では人事・総務担当者がこの方法を選ぶケースも増えています。
なお、紙の控えを手元に残したい場合は、受理済みデータを印刷して社内保管しておくと安心です。
電子申請は効率的かつ正確に届出を行えるため、特に複数拠点を持つ企業にとって非常に有用な方法といえます。
届出を行わないまま放置してしまうと、行政指導や罰金などの法的リスクに発展することがあります。届出義務の意味を理解し、未然にトラブルを防ぐ意識が欠かせません。
就業規則の届出義務があるにもかかわらず、労働基準監督署への届出を怠った場合は罰則の対象となることがあります。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場に就業規則の作成・届出を義務付けており、違反すると30万円以下の罰金が科される可能性があります。
特に注意したいのは、届出の期限が明確に定められていない点です。つまり、就業規則を作成しても、届出を後回しにしてしまう企業が少なくありません。
しかし、監督署の調査や従業員からの申告により、届出がなされていないことが発覚すれば、行政指導や罰則の対象となります。
また、罰則の適用は「故意に届出を怠った場合」が中心ですが、「知らなかった」「忙しくて後回しにしていた」では免責されないこともあります。



行政上の指導を受けた後も改善しない場合には、正式に罰金が科されるケースもあるため注意が必要です。
届出は法令遵守の基本であり、就業規則を作成した時点で速やかに届出を行うことが最も確実なリスク回避策といえます。
届出を怠ると罰則だけでなく、就業規則そのものの有効性が問われる場合もあります。就業規則を整備・届出しないことで発生するリスクについて、こちらの記事で詳しく解説しています。
就業規則の届出を怠った場合や、届出内容が法令に適合していない場合、労働基準監督署からの「指導」や「是正勧告」を受けることがあります。
これらは罰則に直結する前段階の行政対応であり、改善を促すためのものです。
指導・勧告が行われる主なケース
是正勧告を受けた場合は、期限内に改善報告書を提出する義務があります。
対応を怠ると、企業名の公表や刑事罰の対象となる場合もあるため、早急に是正措置を講じることが求められます。
労働基準監督署は「罰するため」ではなく、適正な労務管理を促すために指導を行う立場です。指導を受けた場合は、真摯に対応し、必要に応じて社会保険労務士など専門家の助言を受けながら改善を進めることが大切です。
就業規則は届出を終えた段階で完了ではありません。従業員への周知や、改訂履歴の管理まで適切に行うことで、会社の信頼性と法的有効性を確保できます。
就業規則は、労働基準監督署に届出をしただけでは効力を持ちません。法的に効力を発揮するためには、従業員への「周知」が完了していることが必要です。
労働基準法第106条では、就業規則を労働者に周知させる義務が定められています。つまり、従業員がいつでも内容を確認できる状態を整えておかなければなりません。
(法令等の周知義務)※一部抜粋
労働基準法|e-Gov 法令検索
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(中略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
一般的な周知の方法
特に最近では、紙の掲示に加え、デジタル化された就業規則の共有も認められています。ただし、電子データで周知する場合は、全従業員がアクセスできる環境を確保することが条件です。
もし届出後に周知を怠った場合、就業規則の内容は効力を持たず、会社側の主張が法的に認められない可能性もあります。
たとえば懲戒処分や労働条件の変更を行う際、「周知されていない就業規則に基づくもの」とみなされれば、無効と判断されるケースもあります。
つまり、届出と同じくらい重要なのが、「従業員にきちんと伝わっているか」という点です。周知の方法を社内ルールとして明文化し、新入社員や中途入社者にも常に確認できる仕組みを整えておくことが望ましいでしょう。
就業規則は届出だけでなく、社内への周知をもって初めて効力を持ちます。周知方法や違反時の罰則を詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
就業規則は一度作成したら終わりではなく、法改正や社内制度の変更に合わせて定期的な見直しが必要です。そのため、届出済みの就業規則をどのように保管し、改訂の履歴を管理するかも非常に重要になります。
保管・管理の基本ポイントは以下の通りです。
| 管理項目 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 保管場所 | 受理印が押された写しを本社・人事部などで厳重に保管する |
| 管理方法 | 電子データ化してバックアップを取り、災害時にも復元可能にする |
| 改訂履歴 | 改訂日・変更箇所・届出日を一覧化して履歴を残す |
特に、いつ・どのような理由で改訂したのかを明確に記録しておくことが大切です。後日、労働基準監督署からの確認や、従業員とのトラブル対応時に根拠資料として活用できます。
また、改訂を行う際は、変更内容を明確に示したうえで、再度意見書の聴取と届出を行うことを忘れないようにしましょう。
法令や労働環境は年々変化しています。「3年以上見直していない就業規則」は、現行法とズレが生じている可能性が高いため、定期的なチェックと更新の体制づくりが信頼される労務管理の第一歩です。
就業規則の届出は、企業のコンプライアンス体制を支える基本です。正しい手続きと運用を行うことで、従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。
ここまで見てきたように、就業規則の届出には複数の要件と手順があります。最後に、届出までの基本ステップを整理しておきましょう。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 就業規則の作成・改訂 | 労働基準法に基づき、労働条件や社内ルールを明文化する。必要に応じて専門家に確認。 |
| ② 労働者代表からの意見聴取 | 意見書を取得し、代表者の署名をもらう。手続きの正当性を確保することが重要。 |
| ③ 労働基準監督署への届出 | 管轄署に対し、本則・意見書・届出書を提出。窓口・郵送・電子申請のいずれかで実施。 |
| ④ 従業員への周知 | 掲示や配布などにより、全従業員が内容を確認できる環境を整備。 |
| ⑤ 保管と更新 | 受理印のある控えを保管し、法改正や制度変更のたびに改訂・再届出を行う。 |
これらの流れを正しく踏むことで、就業規則は法的に有効な社内ルールとして認められます。特に、「意見聴取」と「周知」は忘れられがちなステップですが、どちらも就業規則の効力を確保するための必須要件です。
届出までの流れを理解したうえで、変更時の手続きを押さえておくと、法改正や制度変更にもスムーズに対応できます。就業規則変更時の実務手順はこちらの記事で詳しく解説しています。
就業規則の届出方法は、窓口・郵送・電子申請の3通りがあります。どの方法を選ぶかは、自社の規模や運用体制に合わせて判断することが大切です。
就業規則の届出方法まとめ
窓口提出
初めて届出を行う場合は窓口提出が安心です。担当官から直接アドバイスを受けられるため、記載漏れや添付不足を防げます。
電子申請
全国に拠点を持つ企業や、ペーパーレス化を進めている場合は電子申請が効率的です。e-Govを利用すれば、24時間いつでも申請でき、郵送コストも削減できます。
郵送
郵送による届出は、時間に余裕をもって進めれば十分実用的ですが、返信用封筒や切手の準備を忘れないよう注意が必要です。
このように、どの方法を選んでも問題はありませんが、重要なのは「確実に受理され、証拠が残る形で提出すること」です。
届出を怠ると、罰則や是正勧告などの労務リスクに直結します。
就業規則の届出は、会社の信頼性とコンプライアンスを支える基本手続きです。



今後の法改正や組織変更にも対応できるよう、継続的に管理できる届出体制を整えておきましょう。
就業規則の届出は、単なる書類提出ではなく、企業としての法令遵守と労務リスクの予防につながる重要な手続きです。
届け出の義務や方法を正しく理解し、必要書類を整備することで、会社の信頼性と従業員の安心感を高めることができます。
主なポイントを整理すると、次の通りです。
就業規則の届出を正しく行うことで、トラブルの未然防止はもちろん、社員が安心して働ける職場づくりにもつながります。
今一度、自社の就業規則と届出体制を見直し、確実に実務を完了できる仕組みを整備しておきましょう。
当事務所では、就業規則の届出・電子申請・意見書作成・周知までをワンストップでサポートしています。初めて届出を行う方や、書類の不備・対応漏れを防ぎたい企業様からも多くご相談をいただいています。
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っており、オンラインやお電話でも対応可能です。
お申し込みは下記フォームから簡単に行えます。社会保険労務士が貴社の状況を丁寧にヒアリングし、「いま何をすべきか」が明確になる実務的なアドバイスをご提供いたします。
就業規則の届出は、作成・変更・周知など、一連の手続きの中でも重要なステップの一つです。届出だけでなく、就業規則全体の流れを体系的に理解したい方は、下記のまとめページをご覧ください。
就業規則の基礎から改定・トラブル対応まで、専門家の視点で分かりやすくまとめています。